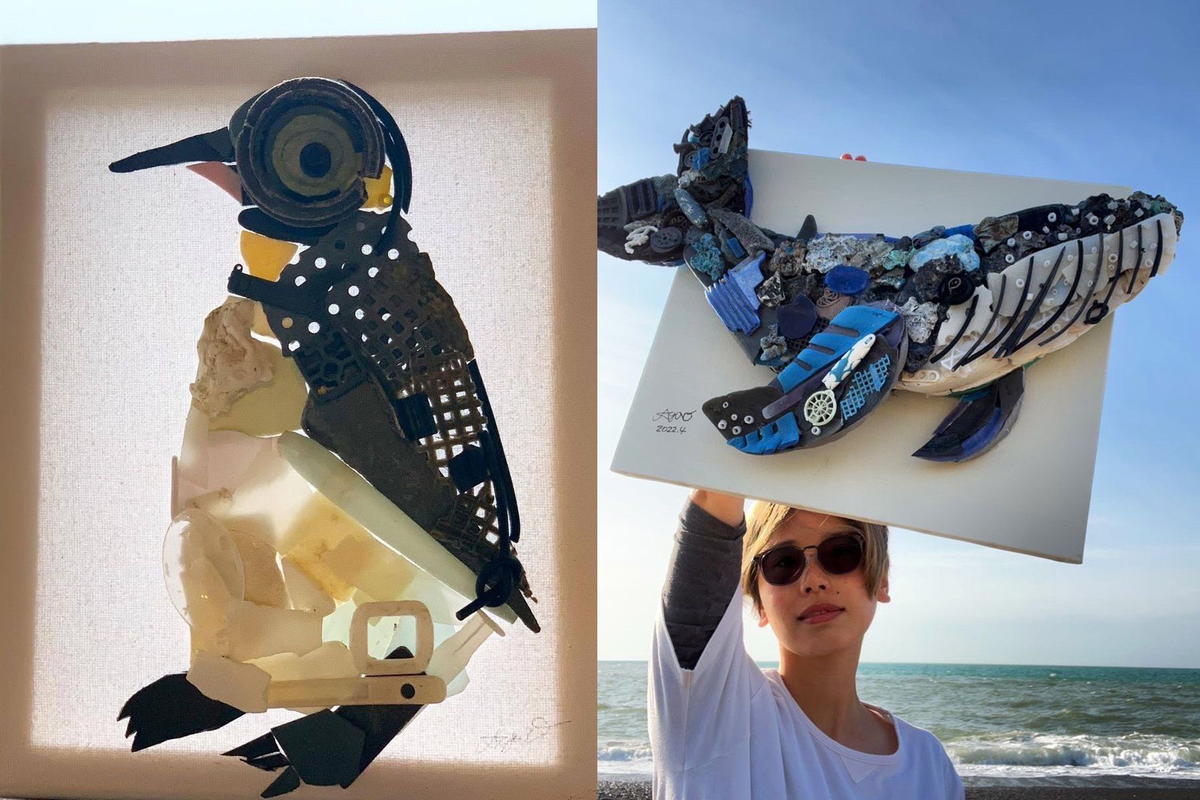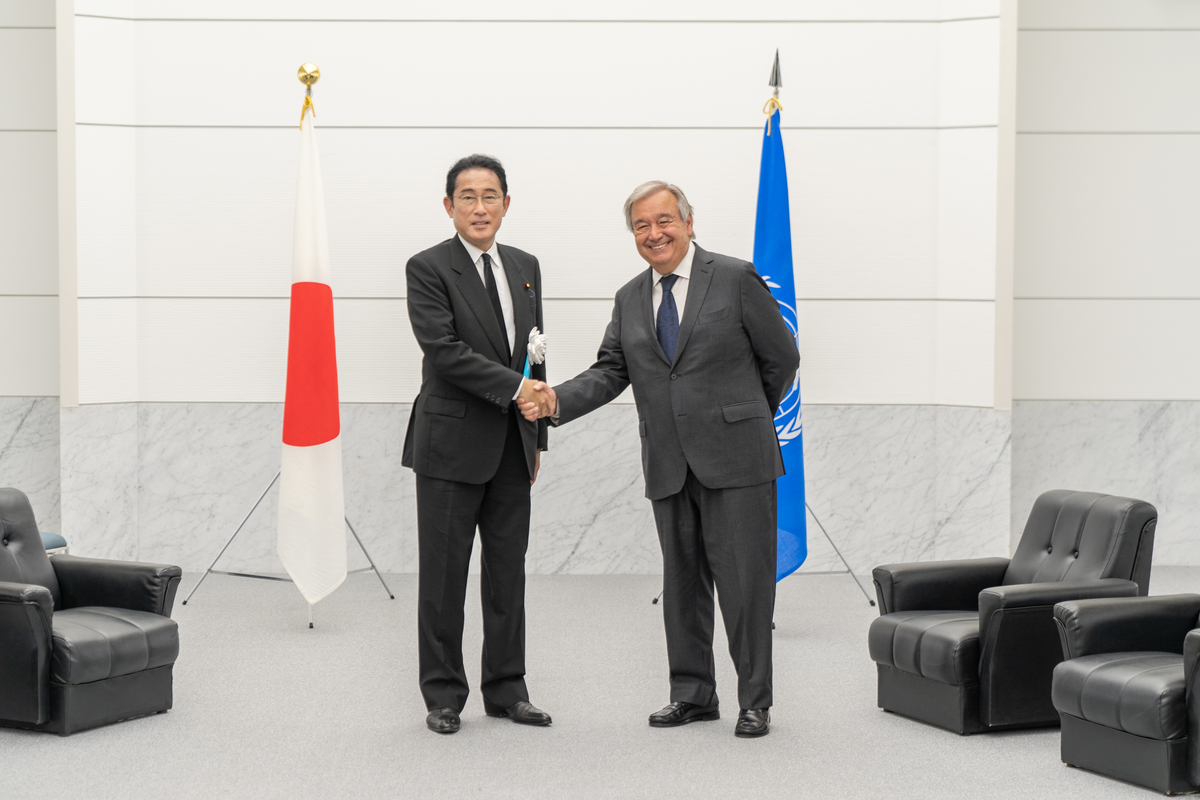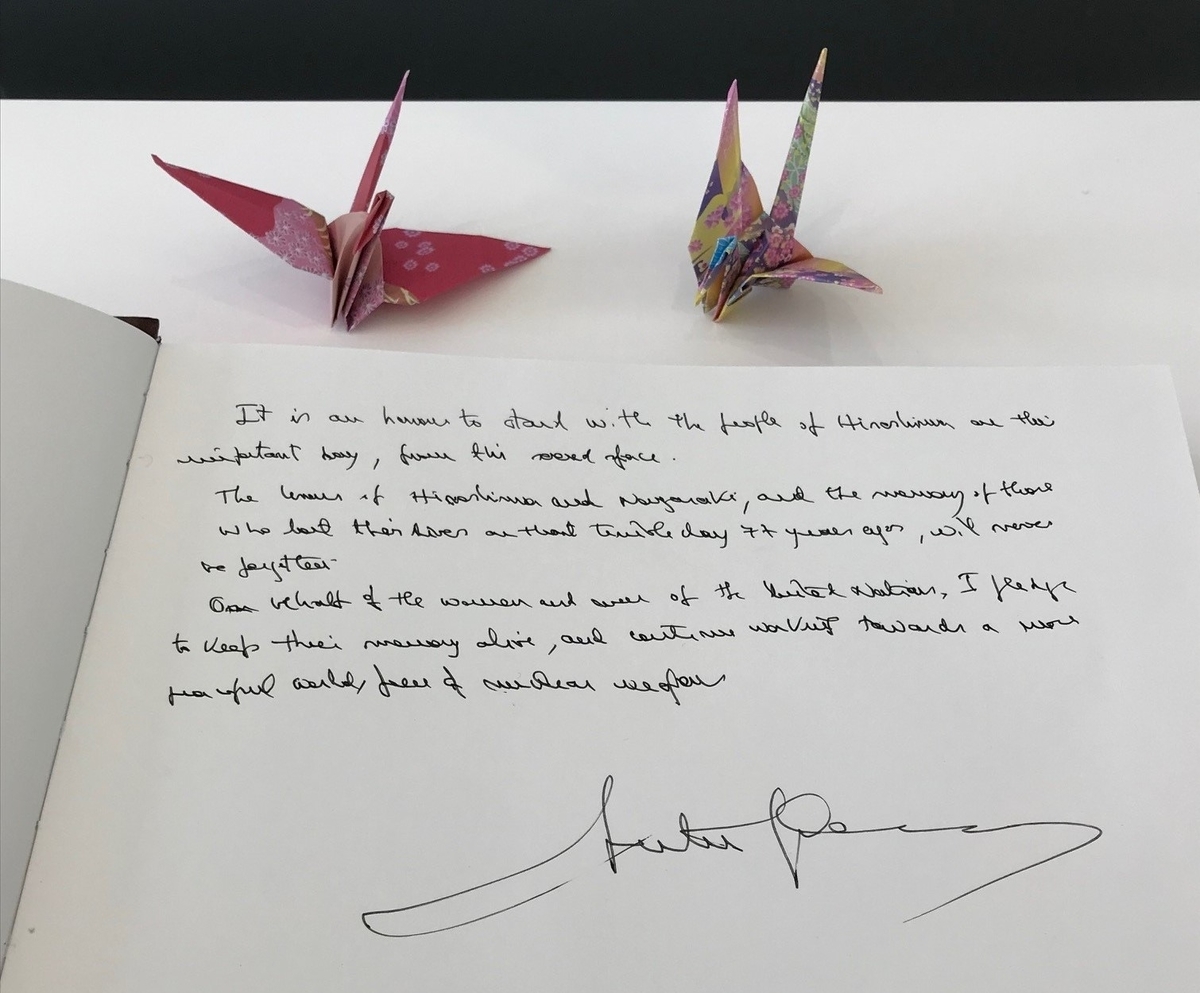11月6日から2週間に渡ってエジプトのシャム・エル・シェイクで開かれた気候変動枠組条約第27回締約国会議(COP27)に、国連広報センターの佐藤桃子広報官が国連グローバル・コミュニケーション局のサポートのために参加しました。世界から約3万5000人が集った過去最大規模のCOPを振り返ります。

「COPが27回も開催されているのに、温室効果ガスが減っていないことに怒りを感じます」
国連機関の代表者がCOP27のある記者会見でこう発言したときに、私はようやく自分が気候変動の課題を真に理解したような気がしました。COPとは、気候変動に人類が立ち向かうための条約の締約国・地域が、気候変動への対応を決めるための会議です。1994年に発効し、現在ほぼすべての国が批准している気候変動枠組条約には明確に温室効果ガスを減らす必要性が書かれているにもかかわらず、この30年間、その目標に人類は近づくところか遠ざかってきたのです。

「損失と損害」基金の設立
皆さんも、COP27のニュースに触れたかもしれません。COPがこれだけ注目を浴びるのは、気候変動が全人類に影響を与え、多くの国の人々が状況が悪化していることを実感しているからです。2023年だけでも国土の3分の1が水没したパキスタンの洪水や、欧州各地で発生した熱波、中国での干ばつといった気候災害が起きましたが、数年前から続いている事象として「アフリカの角」と呼ばれるアフリカ東北部の干ばつや太平洋諸国が直面している海面上昇などもあります。日本も過去最大級の大雨や洪水、台風が年に何度も報じられています。
COP27の成果の一つは、特に気候変動の影響に対して脆弱な開発途上国がうけている「損失と損害」の基金の設立が決まったことです。しかし、「損失と損害」は2023年に出現した言葉ではありません。30年近いCOPの歴史の当初から、開発途上国は気候変動の原因となる温室効果ガスをほとんど排出しない自国が気候変動の影響を最も深刻に受けていることに警鐘を鳴らしていました。しかし、その訴えは30年間放置されてきたのです。
COP27ではパキスタンが積極的に「損失と損害」の深刻性を訴え、ほかの代表団がこの主張に賛同する場面が何度も見られました。そうして「損失と損害」に対する取り組みがようやく始動したのです。

「実行」の必要性と二つのキーワード
ここまで事態を悪化させ温室効果ガスはなぜ減っていないのか?その答えは実行が全く足りていなかったことであり、会場でも実行を妨げている「グリーンウォッシュ」と「資金」の在り方という二つのキーワードが頻繁に聞かれました。

「グリーンウォッシュ」とは実際の行動は不十分なのに環境に良い行いをしていると主張する、見せかけの環境対策を意味します。日本でも政府や自治体、企業などが「脱炭素」や「温室効果ガス排出量正味ゼロ」を目標として掲げていますが、その目標設定と計画、実際の行動は本当に二酸化炭素をはじめとした温室効果ガスを減らせなければ意味がありません。
グリーンウォッシュに対処するため、国連事務総長は今年3月に「非国家主体の排出量正味ゼロ・コミットメントに関するハイレベル専門家グループ」を立ち上げました。COP27ではこの専門家グループが報告書を発表し、環境に関する誠実性、信頼性、説明責任、各国政府の役割について実践的な提言を行いました。例えば、排出量正味ゼロを主張するのであれば、サプライチェーンの一部だけではなく全サプライチェーンで排出量を下げる必要がある、政府の気候変動対策を妨げるようなロビー活動を直接的にも業界団体などを通じて間接的にも行ってはならない、といった提言です。今後、金融業や製造業、サービス業などをふくむすべての産業において、こうした基準が活用されることが期待されています。

「資金」がもう一つの重要なキーワードとなった理由は、資金の流れが今の産業の在り方や、広く使われている技術やエネルギー、社会の仕組みなどを支えているからです。会場で開かれていたファッション業界をテーマにしたイベントでも、衣服を製造する企業が「この10年間エネルギー消費量の削減など努力はしてきましたが、それでは正味ゼロ目標を達成できないなことはわかっています。再生可能エネルギーへの転換が必要で、そのためには資金が必要なのです」と率直に話していました。産業の在り方や再生可能エネルギーへの転換以外にも、早期警報システムなど気候変動の影響への適応策の強化、女性など気候変動対策に参加する権限や資源を使うことが制限されているグループへの支援などを実行するには資金が必要です。

先の専門家グループのメンバーである三宅香さん(日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)共同代表)も「行動を後押しするには、やはりお金が大事です。何にでもお金を出せば良いわけではなく、お金の流れを大きく変えなければなりません。金融業界への期待は高く、同時に厳しい目も向けられています」と話してくれました。
#COP27 現場より: 国連事務総長が立ち上げた、 排出量正味ゼロに関する専門家グループの一員の三宅香さん (日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP) 共同代表)は5年ぶりにCOPに参加。
— 国連広報センター (@UNIC_Tokyo) November 13, 2022
「COPの主眼が、気候変動に『なぜ』取り組み『何を』すべきかという点から『行動』に移りました」と言います。 pic.twitter.com/BMRtOCyMNa
さまざまなプロセスを経ることになる「公正な移行」
COP27の会場では、誰もが気候変動に歯止めをかける必要性を理解していました。他方で、「温室効果ガス正味ゼロ」にむけてどう進べきなのかという点についてはさまざまでした。背景には状況の違いがあります。たとえば、アフリカ諸国には、電気を使える人々が人口の10%以下しかいない国々があります。再生可能エネルギーに転換できるのは何年後なのか、それまでの期間はどのエネルギーをどう使って電気の普及率を上げるのか?また、こうした国々は気候変動の影響に対応する仕組みや人材、インフラ等が不十分なのでその対応も急務ですし、国の中には女性や先住民など特に取り残されているグループもいます。対処すべき課題はたくさんあります。

一つだけ明確なことは、私たちが実現しなければならない変化は一朝一夕で成し遂げられないからこそ、早く始めなければならないということ。30年もの間、十分対応できてこなかった代償を、私たちはいま身をもって払っています。これ以上の実行不足は、さらなる犠牲を招くだけです。
会場では、科学者、国際機関、島嶼国などのグループ、そして市民社会が深刻な現実と世界の平均気温上昇を1.5℃に抑える必要性を連日訴えていました。国連開発計画(UNDP)で各国の気候変動対策の策定や実施を支援している山角恵理さんは「多くの島嶼国や開発途上国にとって1.5℃は数字ではありません。自分達の生存に関わる、まさにサバイバルのための上限です。各国がそれをどれだけ本気で捉えているのかが問われています」と話していました。
交渉の行く末
COP27は18日(金)に閉幕する予定でしたが、交渉が難航していることは早い段階で明白でした。「損失と損害」基金の方向性は示されるのか、前回のCOP26でグラスゴー(COP26開催地)の合意文書に含まれた1.5℃という努力目標を今回も維持できるのか、私もハラハラしながら最新情報を追っていました。
気候変動を引き起こすのも対応するべきなのも、政府だけではありません。企業などさまざまな非国家主体もプレーヤーです。しかし、この条約において最終的な意思決定を行えるのは締約国・地域だけです。市民社会は連日、イベントや記者会見、デモといった形で、締約国・地域の責任を問うだけでなく協力を求め続けました。同時に、交渉の進捗状況を随時アップデートしてオンラインで公開する団体もいたり、各地から集まったメディアが多種多様な言語で会場の声を世界に発信したりと、会議の透明性を高める動きも続きました。


そうして、皆が見守る中、最終会合が現地時間の20日(日)午前3時ごろに始まりました。再度検討を行うために一時中断する場面もありましたが、サーメハ・シュクリCOP27議長(エジプト外相)がコンセンサス方式でまとまった成果文書を読み上げた時には、ほっとしました。しかし、成果文書の課題も多数指摘され、締約国間がこれからも交渉をおこない、実質的な調整を進めていく必要性が確認されました。同日午前9時半ごろにCOP27は遂に閉幕しました。
COP27はイベントではなく真剣勝負の交渉の場で、いくつも印象的な場面がありました。その中でも、当初の最終予定日であった18日に開かれた代表団の会合で、ガーナの代表団として出席していた10歳の気候活動家Nakeeyat Dramani Samさんが「熱意をもって、ちゃんと考えてください」と訴えた時に心が震えたのを覚えています。自分のコミュニティーが気候変動の影響を受けていることを踏まえ、「皆さんが私のような若者だったのなら、この時点で地球を救うために必要な合意に達しているのではないでしょうか?若者が議論を主導したほうが良いのでしょうか?」としっかりとした口調で問いかけました。これが経験や思慮の浅い訴えだと捉えた人はあの場にいなかったでしょう。

気候変動は非常に深刻で大規模な課題です。誰も逃れることができず、悪化の一途をたどっています。画期的な「損失と損害」基金は事後的対応でしかなく、各国政府の気候変動対策である「自国が決定する貢献(NDC)」はまだまだ強化が必要です(COP26閉幕からCOP27開幕までにNDCを強化あるいは新しく提出した締約国は30未満でした)。
COP27では、それでも気候変動に正面から挑む人々の確かな連携をみることができました。こうした人々は一時的にエジプトに集っただけで、普段は世界各地で活動しています。日本にももちろんいます。そうした人々の数が増え、気候変動を真に食い止める流れに変わることを切に願うとともに、国連の重責を感じながら帰国の途に就いた出張となりました。
COP27や気候変動についてもっと学びたい方は、ぜひこれらのページをご覧ください。